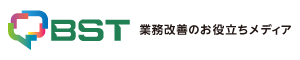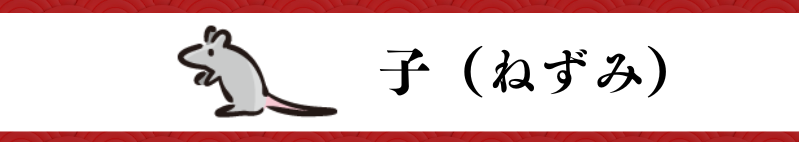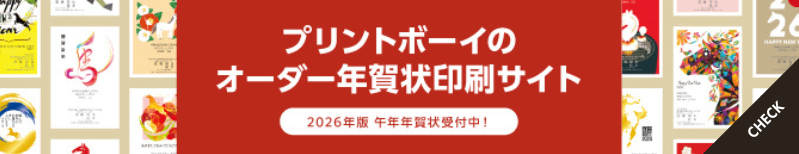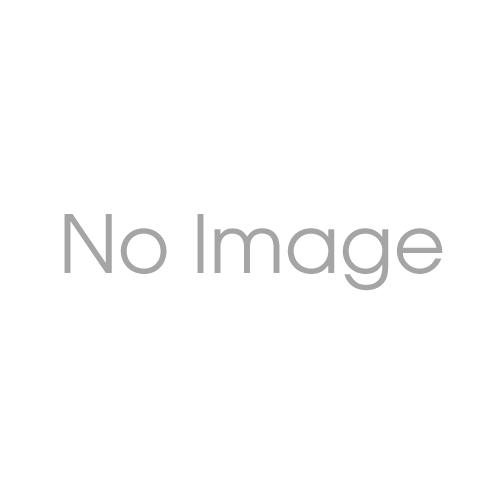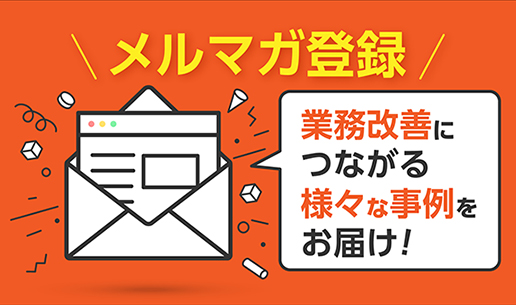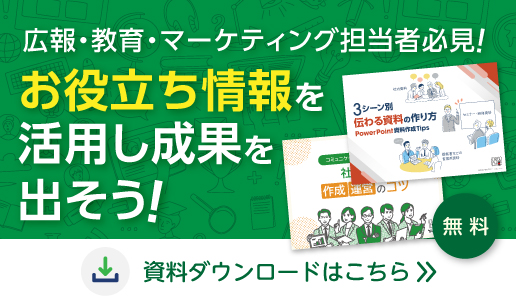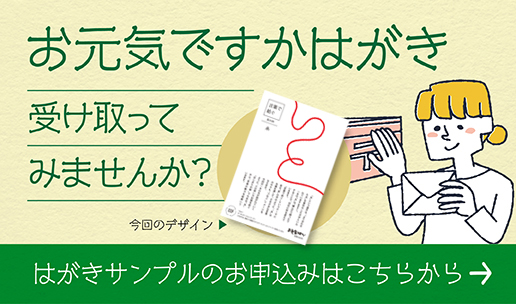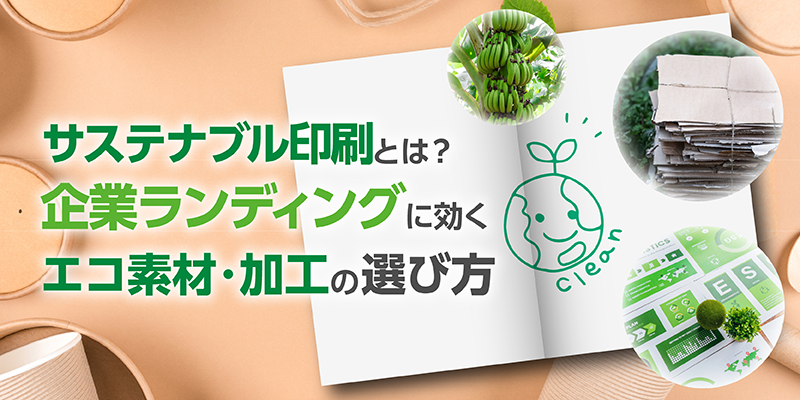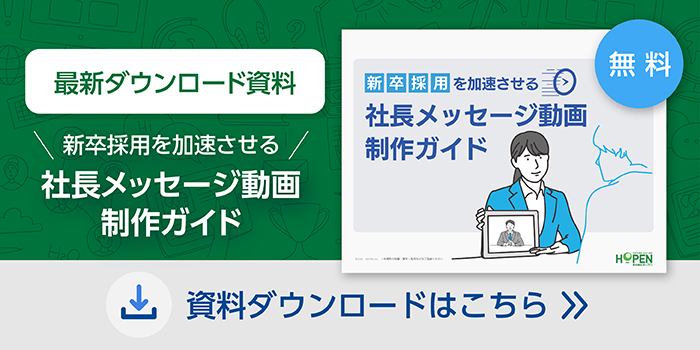年賀状を書く際に特に意識するのが十二支(じゅうにし)。自分が生まれた十二支の年になると「年男」「年女」などと呼ばれ、現在でも馴染み深いものですよね。
今年の2025年は巳(み)年、来年の2026年は午(うま)年です。
では、この十二支はいつ生まれたのか、なぜこの順番なのかご存知でしょうか?
今回は、知ると面白い十二支について、十二支の順番の意味と、それぞれの意味について解説します。
◆目次
1.十二支とは

1-1.十二支に込められた想い
十二支とは、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)の12種からなります。
日本ではねずみ、うし、とら……と12の動物を当てはめたものが知られており、年賀状のデザインや、生まれ年を表現するときなどに用います。
この十二支には、当てはめられたそれぞれの動物に様々な思いが込められています。
子(ねずみ)
すぐに子ねずみが増え成長することから、子孫繁栄の意味があり、「行動力と財」を表します。
丑(うし)
肉は大切な食料に、力は労働にと社会に密接に関わることから、「粘り強さと誠実」を表します。
寅(とら)
寅(虎)は毛皮の美しい模様から前身は夜空に輝く星と考えられ、「決断力と才知」を表します。
卯(うさぎ)
うさぎの穏やかな様子から家内安全、跳躍する姿から飛躍を表し、「温厚で従順」な特徴を持ちます。
辰(りゅう)
伝説の生き物である龍は、古来中国では権力者の象徴として扱われました。「正義感と信用」を表します。
巳(へび)
執念深いと言われる蛇ですが、助けてくれた人には恩返しを行うと言われています。「探究心と情熱」を表します。
午(うま)
人との付き合いが古い動物で人の役に立ち、人間も馬を大事に扱いました。「陽気で派手好き」という特徴を持ちます。
未(ひつじ)
群れをなす羊は家族の安泰を示し、いつまでも平和に暮らす事を意味しています。「穏やかで人情に厚い」という特徴を持ちます。
申(さる)
山の賢者で、山神の使いと信じられていました。信仰の対象としても馴染み深い動物です。「器用で臨機応変」という特徴を持ちます。
酉(とり)
人に時を報せる動物で、「とり」は“とりこむ”と言われ、商売などには縁起が良いとされています。「親切で世話好き」という特徴を持ちます。
戌(いぬ)
社会性があり忠実で、人との付き合いも古く親しみ深い動物です。「勤勉で努力家」という特徴を持ちます。
亥(いのしし)
猪の肉は万病を防ぐといわれ、無病息災の象徴とされています。「勇気と冒険」を表します。
こうして見ると、十二支にもそれぞれちゃんとした意味があることが分かりますね。
1-2.なぜ干支はこの順番に?

十二支はなぜこの子・丑・寅……の順番になったのでしょうか。
皆さんは、十二支の由来に関する説話をご存知ですか?
大昔の話。神様が「一月一日の朝、一番から十二番目までに来たものを1年交代で動物の大将にする」という手紙を書きました。
それを受け取った全国の動物たちは、自分が一番になろうと翌朝まだ暗いうちから一斉にスタートしました。でも猫だけは「一月二日の朝」とネズミから聞いていたので、出発しませんでした。
犬と猿は最初こそ仲良く並んで走っていましたが、次第に必死になり、とうとう丸木橋の上で大げんかを始めてしまいました。
いよいよ新年の太陽が昇った時、前日の夕方から出発していた牛が一番に現れました。
しかし牛の背に乗っていたネズミが、「神さま、新年おめでとうございまチュウ」と、牛の背中からぴょんと飛び下り、神さまの前に走っていきました。
一番はネズミになってしまったので、牛は「モゥモゥ!」と悔しがりました。
続いて虎が到着し、そして兎、龍がやってきました。こうして次々に動物たちが到着し、蛇、馬、羊、猿、鳥、犬、猪、カエル、の順番となりました。
13番目になってしまったカエルは、がっかりして「もうカエル」と言って帰っていきました。
さて、神さまと十二支たちの酒盛りが始まりましたが、犬と猿はまだケンカをしていました。
そこへ、すごい剣幕で猫が現れ、ネズミを追いかけまわしました。だから、今でも猫はネズミを追いかけていて、犬と猿は仲が悪いという事です。
順番だけでなく、十二支に猫がいない理由や「犬猿の仲」の語源などがわかるお話ですね!(ちなみに、鳥がケンカの仲裁に入ったので猿、鳥、犬の順番になったと言われているそうです。)
この昔話は、十二支を採用している中国、朝鮮半島、モンゴル、中央アジア、ロシア周辺などにも伝わっており、ほとんどのものが「猫とねずみが敵対することになった十二支の話」もしくは「ねずみが牛にくっついていって一番になる十二支の話」であるそうです。
作者は、よっぽど猫が苦手だったのかもしれません。
…といったように一般的にはこの説話で親しまれている十二支ですが、実は始まりは動物と全く関係がなかったのです。
1-3.もともとは数詞だった!
それでは、十二支の始まりとはいつなのでしょうか。
いつ頃始まったのかは定かではありませんが、中国の殷時代(紀元前17世紀頃~紀元前1046年)の遺跡から発見された甲骨文には十干(じっかん)と組み合わされた表があり、日付を記録するのに利用されていたといわれています。
中国の戦国時代(紀元前 403~221 年)以降、日付だけでなく、年・月・時刻・方位にも利用されるようになります。
古代中国の天文学においては、木星が約12年で天を1周することから、天を西から東に12分割し、毎年度における木星の運行と位置を示していました。
つまり十二支は、十二年で天を一周する木星の軌道上の位置(天の位置)を示すための数詞だったのです。
そして、中国の後漢時代(建武3年(27年)~永元9年(97年)頃)に王充(おうじゅう)という人が民衆に十二支を浸透させるべく、数詞を覚えやすく馴染みやすい動物に替えて文献を書いたことから、前述した十二支の説話が広まっていきました。
2.十二支と干支の違いとは?

ところで、皆さんは「十二支」と「干支(えと)」の違いはご存じですか?
私たちが普段、「干支」と呼んでいるのは、実は正確には十二支(子・丑・寅…)のことです。
しかし、本来の「干支」とは、「十干(じっかん)」と「十二支」を組み合わせたもので、次のような関係になっています。
●十干(じっかん)
甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)
己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)
→10種類の陰陽思想に基づく数詞として、古くから使用されてきました。
ちなみに、「干支」を「えと」と読むのも、十干の「兄(え)」と「弟(と)」の読み方が由来といわれています。
兄=陽、弟=陰 を意味していて、「万物は陰と陽に分類される」といった陰陽の思想が反映しているのだそうです。
●十二支
子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
→12種類の動物で年や方位を表しています。
この「十干」と「十二支」を順番に組み合わせると「甲子(きのえね)」「乙丑(きのとうし)」…と続きます。そして60組目の「癸亥(みずのとい)」で終わり、60通りの組み合わせができます。
60個すべてが終わると最初の「甲子」に戻り、60歳で祝う「還暦」は、この干支が一巡し、誕生年(暦)の干支に還ることから来ている文化で、現在でも引き継がれています。
「十干」とだけ聞くと、あまり馴染みが無いように感じられますが、還暦の文化以外にも「甲乙つけがたい」など私たちの生活の中にも十干を用いる場面は多々あります。
3.まとめ

私たちの生活に馴染み深い十二支について、より詳しく解説しました。
来年(2026年)の十二支は午(うま)年。「陽気で派手好き」な特徴をもつ馬は前向きで活発な1年へと私たちを導いてくれるでしょう。
そんな新年のスタートは、年賀状で大切な方へのご挨拶から始めませんか。
弊社ホープン(旧社名:プリントボーイ)では、約50年間にわたり年賀状を企画・販売してきました。
今年の十二支「午」の可愛らしい温かみのあるデザインから、スタイリッシュなアートデザインまでお客様のニーズにお応えした年賀状を各種取り揃えております。
ぜひ、プリントボーイの年賀状で素敵な新年をお迎えください!
▼ 参考サイト
▼ こちらもあわせてお読みください