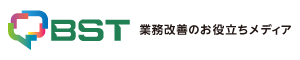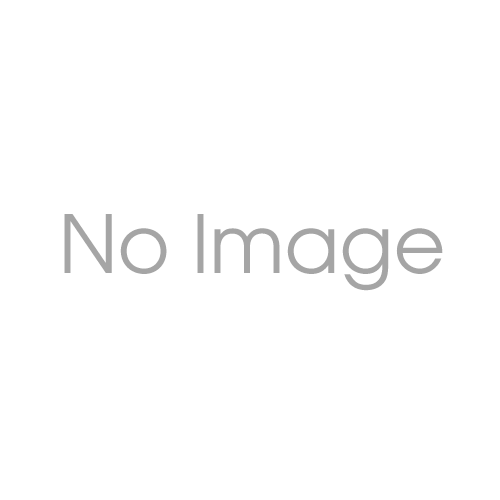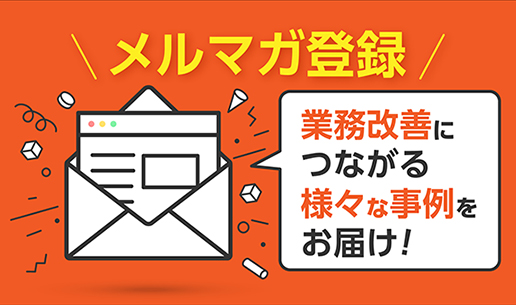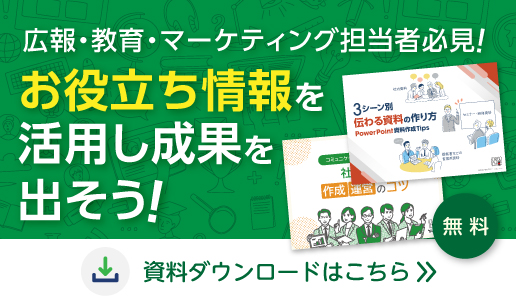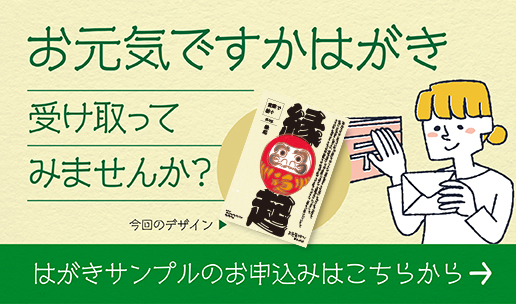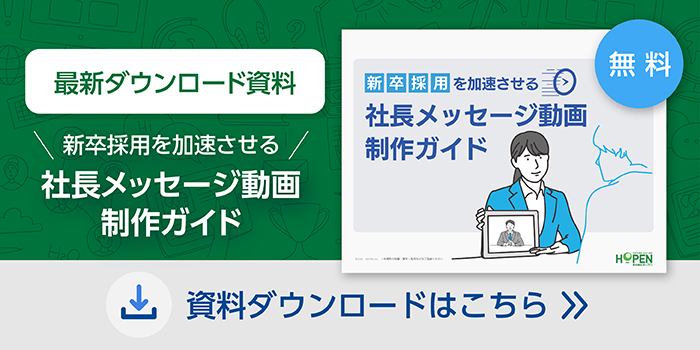採用してもすぐに辞めてしまう、せっかく育った人が他社へ移ってしまう…。昨今、人材の流動化が進む中、企業が本気で取り組むべきことは“採用”よりも“定着”です。
社員が「この会社で働き続けたい」と感じる企業には、偶然ではなく“辞めない仕組み”があります。それが今回ご紹介する「リテンションマネジメント」です。
本記事では、人材の定着を「経営戦略」として設計するための考え方から、心理的安全性・キャリア支援・組織文化といった定着率を高める3つの視点についてご紹介します。
◆目次
1.リテンションマネジメントとは?
「リテンションマネジメント」とは、採用した人材が組織に長く定着し、意欲的に働き続けられるようにするための“定着を設計するマネジメント”のことです。
従来の人事施策は「採用=ゴール」となりがちでしたが、これからの時代は「採用=スタートライン」と捉える発想が求められています。
1-1.採用・育成・評価をつなぐ“定着戦略”の考え方
「リテンションマネジメント」で必要なのは、“入社後の体験設計”です。入社後の「オンボーディング(受け入れ)(※)」からキャリア支援、評価・承認の仕組み、そして学び続けられる環境づくりまでを、一つの流れとしてデザインすることが、従業員の定着率を高めるためのポイントです。
(※)「オンボーディング」に関して気になる方は以下の記事をご覧ください。
▼「オンボーディング」に関する記事はこちら
オンボーディングとは?安心して働くために準備したい10の施策
そんな中、多くの企業が陥りがちなのは、「採用」「教育」「評価制度設計」が各チームバラバラに動いてしまうこと。
それが結果的に、社員が「入社前に聞いていた会社の姿」と「入社後の実体験」の間にギャップを感じてしまい、早期離職やモチベーション低下を招いてしまいます。
「リテンションマネジメント」は、これらを一本の“従業員ライフサイクル”として再設計し、採用・育成・評価を横断してつなぐ、戦略的な仕組みを整えることを目的としています。
※従業員ライフサイクルに関してご興味がある方は以下の記事をご覧ください。
▼「従業員ライフサイクル」に関する記事はこちら
採用・定着・エンゲージメントの強化に!「従業員ライフサイクル」接点ごとに何が必要!?
1-2.「個人の幸せ」と「組織の成果」を両立するための経営視点
リテンションマネジメントは、「すべての人を無理に引き留める」ことを目的とするものではありません。
人には、それぞれのキャリアのタイミングや価値観があり、中には“次のステージで活躍すること”が本人にとって幸せである場合もあります。
その際に、経営として重要なのは「誰を引き留め、誰を送り出すか」を見極めることです。
貢献意欲が高く、価値観やビジョンを共有できる人材には、成長や挑戦の機会を提供し、長く活躍してもらう仕組みを整えましょう。
一方で、方向性が明確に異なる人材には、お互い納得して新たな道を応援する“前向きな出口設計”を用意することも選択肢です。
そうした積み重ねにより「残る人がより誇りを持てる組織文化」を育て、結果的に定着率だけでなく組織の健全性そのものを高めていくことにつながります。
1-3.採用・教育・経営企画が連携すべき理由
「リテンションマネジメント」を成功させるには、人事だけでなく、経営・教育・現場マネジメントが一体となって取り組むことも欠かせません。
採用段階で描いた「企業の約束」を、教育で体験に変え、評価制度で支えるという一貫した流れがあってこそ、社員のエンゲージメントは継続します。
特に経営企画や広報部門は、“会社の理念やビジョンをどのように言語化し、社内外に伝えるか”という点で重要な役割を担います。
理念と制度、言葉と行動を一致させることができれば、社員は「この会社の一員であること」に誇りを持ち、自然と企業のブランド価値を高める担い手になります。
2.定着率を高める3つの視点
「人が辞めにくい会社」は偶然ではありません。今回のテーマである「リテンションマネジメント」の設計によって生まれています。
定着率を高めるには、「給与」や「福利厚生」も大事ですが、それ以外にも社員が「ここで働く意味」を感じられる環境を整えることが必要です。ここでは、環境を整えるための3つの視点をご紹介します。
2-1.心理的安全性(“安心して意見を言える環境”の設計)

まず定着に重要なのは、社員が安心して意見を発信できる“心理的安全性”の確保です。
チームの中で「否定されない」「意見を言っても大丈夫」という空気があると、社員は自分の考えを表現しやすくなります。
この小さな安心感の積み重ねが、「エンゲージメント」と信頼関係を育てていきます。 “心理的安全性”を高めるには、具体的に次のような取り組みが効果的です。
- 上司と部下の1on1ミーティングで「意見を聞く時間」を確保する
- ミスを責めるのではなく「学びの共有」として扱う文化をつくる
- 社内SNSや意見投稿ツールなど、声を上げやすい仕組みを作る
これが「離職防止」だけでなく、イノベーションや成長の土台にも影響します。
2-2.キャリア支援(成長実感を生むフィードバックと1on1)

2つ目の視点は「成長実感」を感じられるキャリア支援です。人は「自分が成長している」「期待されている」と感じたときに、やる気が高まるといわれています。
逆に、「何を求められているのか分からない」、「評価が不透明」といった状況では、早期離職のリスクが高まります。
そのため、リテンションの観点では“評価”を「査定」ではなく「対話」として設計することがポイントです。
近年、多くの企業が導入している1on1ミーティングは、その代表的な仕組みといえます。
1on1では、上司と「成果の確認」だけでなく「キャリアの方向性」や「やりがいの源泉」を一緒に探ることが求められます。
また、社員が自らの強みや課題を言語化できるよう、フィードバックを「指摘」ではなく「支援」として届けることが重要です。
●キャリア支援で必要なこと
- 定期的なキャリア面談で“成長目標”を共有する
- 成果だけでなく“努力・学び”を評価項目に含める
- 小さな達成も称賛し、自己効力感を高める
こうしたフィードバック設計があると、社員は“自分の成長を会社が見てくれている”と感じ、結果として定着率の向上につながります。
2-3.組織文化(共感できる理念・ビジョンの浸透)

最後3つ目の視点は、「文化の共有」です。いくら制度が整っていても、「理念」や「ビジョン」に共感できなければ、人は長くとどまりません。
「リテンションマネジメント」においては、理念を“掲げる”だけでなく“体験として浸透させる”ことが大切です。そんな中でカギを握るのが社内広報の力です。
社内報・動画・インタビュー・社内イベントなどを通じて、社員が自社の理念や行動指針を「自分ごと」として感じられる発信を行うことで、文化が根づいていきます。
例えば、
- 経営者や社員のストーリーを「社内報」で紹介する
- 経営理念を“行動に移している人”を社内で称える表彰制度
- 「理念×行動」をつなぐ動画コンテンツの発信
※「カルチャーマッチ」についてご興味がある方は以下の記事もご覧ください。
▼「カルチャーマッチ」に関する記事はこちら
なぜ人材定着に「カルチャーマッチ」が重要なのか?
3.リテンションを仕組み化する実践例
日常のコミュニケーションや体験設計の中にも、“働き続けたいと思える瞬間”を意図的に組み込むことができます。
ここでは、定着を支える仕組みづくりの事例を4点ご紹介します。
3-1.「オンボーディング」プログラムの再設計
新入社員が最も不安を感じるのは、入社直後の「自分の居場所が見えない時間」です。
この時期に“何を学び、誰と関わり、どんな支援があるか”を明確にしておくことが、定着率に直結します。
例えば、入社から90日間を「学びと成長のロードマップ」として可視化し、1週間ごとの学習テーマと目標を設定しましょう。それを、メンターや上司がチェックシートで進捗を確認できる仕組みを導入することで、入社後どのように業務を進めればいいのか理解することができるため、“安心感”につながります。そうすることで、3ヶ月以内の早期離職のリスクを減らす効果が期待できます。
新入社員が最も不安を感じるのは、入社直後の「自分の居場所が見えない時間」です。
この時期に“何を学び、誰と関わり、どんな支援があるか”を明確にしておくことが、定着率に直結します。
例えば、入社から90日間を「学びと成長のロードマップ」として可視化し、1週間ごとの学習テーマと目標を設定しましょう。
それを、メンターや上司がチェックシートで進捗を確認できる仕組みを導入することで、入社後どのように業務を進めればいいのか理解することができます。
ロードマップを知ることで、成長のプロセスを感じることができ“安心感”につながります。そうすることで、3ヶ月以内の早期離職のリスクを減らす効果が期待できます。
※「オンボーディング」に関して気になる方は以下の記事をご覧ください。
▼「オンボーディング」に関する記事はこちら
オンボーディングとは?安心して働くために準備したい10の施策
3-2.“称賛の見える化”がエンゲージメントにつながる
積極的に感謝をする文化があることで、組織の空気が変わります。例えば、社員同士が「ありがとう」と言葉で感謝の気持ちを伝えたり、カードで送り合う「サンクスカード制度」があると、小さな行動を認め合う文化を育てることができます。そうすることで、「心理的安全性」を高める施策につながります。
また「承認」が可視化されることで、“自分の行動が誰かの役に立っている”という実感が生まれ、モチベーションがアップし、自走するサイクルが形成されます。
ある企業では、「サンクスカード」の投稿を社内のイントラで共有したところ、部署を超えた交流が増え、「社員満足度」が向上したという結果につながった事例もあります。
3-3.社員インタビュー動画の社内共有
採用広報で使われる「社員インタビュー動画」ですが、社内にも活用する企業が増えています。
例えば、“働く理由”や“挑戦のストーリー”を語る動画を社内ポータルに掲載することで、社員同士が互いの価値観を知り、職場への誇りが高まる効果も期待できます。
言葉だけでは届きにくい“感情の温度”を伝えることができるのが、動画という社内コンテンツの強みです。
3-4.データと心理の両輪で“定着”を管理する
リテンションは感覚ではなく、データと対話の両面で把握することが重要です。
例えば、エンゲージメントサーベイによるスコアの可視化と、上司と部下の1on1ミーティングを月1回30分以上ルール化した企業では、「キャリア相談」の機会が増え、離職率が改善したという報告もあります。
“数字”で組織の温度を測り、“対話”で温度を上げる。この2つの取り組みを行うことで、再現性のある経営施策になります。
「エンゲージメントサーベイ」でスコアの可視化のみを行っている場合は、対策として「対話」を取り入れて改善を図ってみるのはいかがでしょうか。
4.“社内コンテンツ”が定着を支える
人が定着する組織には、「自分の存在が会社の物語の一部になっている」という実感があります。それをカタチにするのが、社内発信です。
4-1.社内報・動画・メッセージが生む“信頼と共感”
定期的な社内報や、トップメッセージ動画は、単なる情報共有ではなく“信頼を積み重ねるツール”の一つです。
経営層の言葉や社員の努力がストーリーとして届くことで、「会社に大切にされている」「この会社を一緒につくっている」という共感が生まれます。
また、従業員データやアンケート結果と連動させることで、個々のニーズに合わせたパーソナライズ施策も可能になります。
その結果、採用から定着までの人材育成コストを削減し、人的資本の最大化に貢献します。
4-2.“社員の声”を活かすことが離職防止につながる
一方的な広報ではなく、社員の声を拾い上げ、記事や動画として発信することも重要です。
社員が主役になれる発信体験は、エンゲージメントを高め、“発信=貢献”という新しいモチベーションを育てることにつながります。
「ブランディング」について詳細が知りたい方は以下の記事もご覧ください。
4-3.コンテンツ制作を仕組み化することで文化を“見える化”する
感覚的な“良い雰囲気”ではなく、理念や行動指針を具体的なエピソードや、ビジュアルで伝える仕組みを持つことが、文化を「再現できる状態」に変えます。
例えば、「ブランドブック」や「社内報」、「社員インタビュー動画」、「表彰」制度などは、“人が辞めない理由”を日常的に可視化するツールになります。
5.まとめ|「設計された安心」で人材の定着を図りませんか?
人が定着する会社は、偶然ではなく「設計された安心感」で成り立っています。
入社後の体験や、日々の称賛、キャリアの対話、そして理念を共有する発信などが積み重なることの全てが、社員に「ここで働く意味」を感じさせる要素になります。
「リテンションマネジメント」は、人事部門だけでなく経営・教育・広報を巻き込み、“人が成長し続ける仕組み”を組織全体でデザインしていく考え方です。
リテンションマネジメントの成功には、制度だけでなく社員の想いや文化を“見えるカタチ”で伝え続けることが大切です。
数字で管理するだけでなく、信頼・共感・誇りを生む仕掛けを作ることが、定着の戦略になりますので、取り入れられそうなことから、始めてみるのはいかがでしょうか。
ホープンでは、採用から定着・育成まで、人と組織の物語をつなぐ、ブランドブックや社内報、社員インタビュー動画など、コンテンツづくりを企画から・制作までご支援しています。
企業理念やカルチャーを社内外に伝えるためのコンテンツ制作に関するご相談がありましたら、ホープンにお気軽にご相談ください。
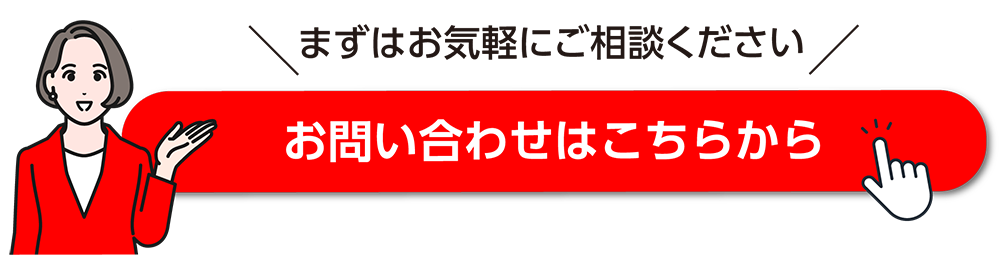
▼\おすすめ/採用動画に関するホワイトペーパー
自社に最適な採用動画の種類や活用事例をお悩み別におすすめをご紹介!簡単入力で入手ください。
人事・採用ご担当者様向け「採用動画制作ガイド」
実写?アニメーション?目的別の動画の使い分けガイド
人事・採用ご担当者様向け「社員インタビュー動画実践ガイド」
▼この記事を読んだ方はこちらの記事もおすすめ!