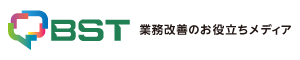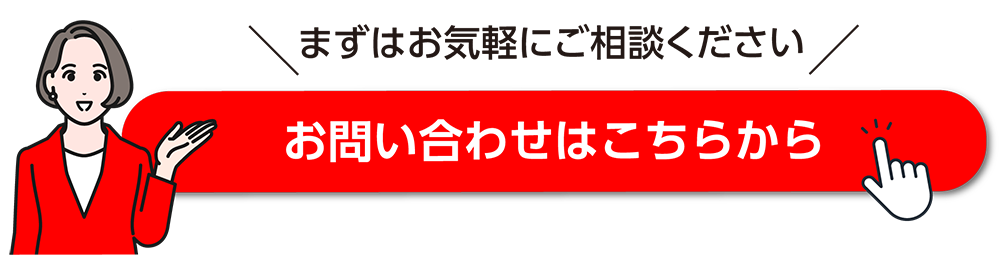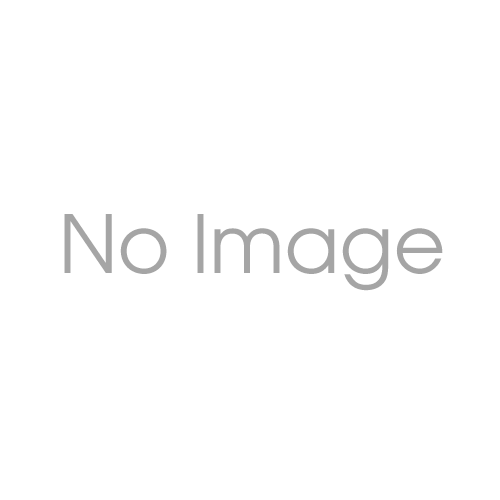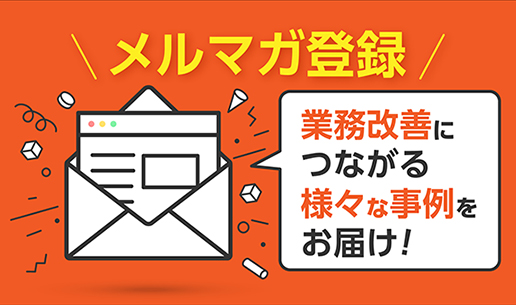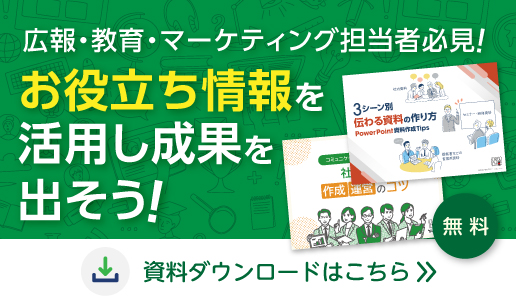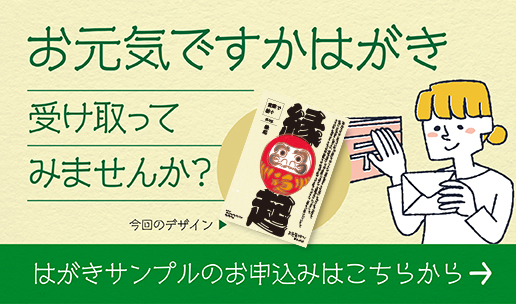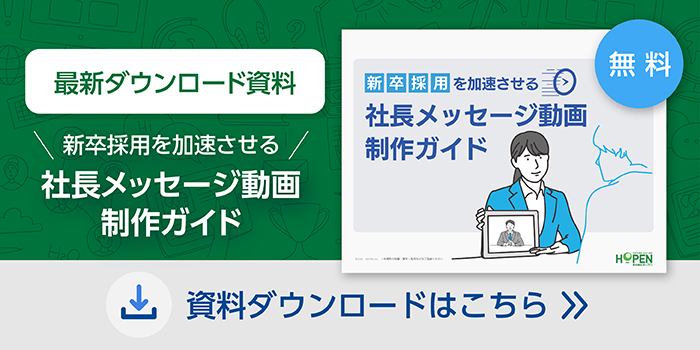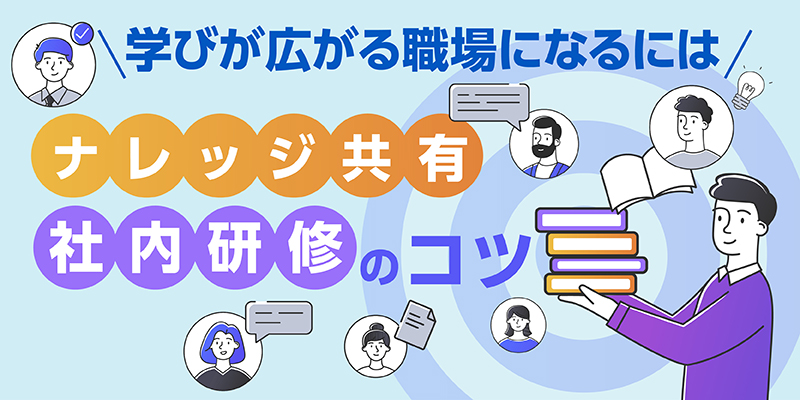
研修を実施しても、「現場で活かされない…」「一過性で終わってしまう…」そんな課題を抱えていませんでしょうか。
そのお悩みを解決するには、“研修を仕組み化”し、社員同士の学びを循環させることです。
この記事では、学びを文化として定着させるためのナレッジ共有・社内研修のコツをご紹介します。
◆目次
1.“学びの仕組み化”が求められる背景
1-1.知識が陳腐化するスピードが速くなったことで学び続けることがより重要に
生成AIをはじめとしたテクノロジーの急速な進化により、「一度覚えた知識やスキル」が長く通用しなくなってきました。
さらに、働き方の多様化やグローバル競争の加速といった外的要因も重なり、企業を取り巻く環境は年々複雑化しています。
こうした変化により、常に新しいスキルや知識を身につけることが求められる時代になりました。
かつては「一度研修を受ければ十分」と考えられていたかもしれません。
しかし、今では意識して学び続ける姿勢がなければ、企業も個人もすぐに時代の変化に取り残されてしまいます。
だからこそ、“学び続ける仕組み”を組織として整えることが、今まさに求められているのです。
1-2.「学び=個人の努力」から「学び=組織文化」への転換
これまで多くの企業では、「学び」は個人の意欲や自己啓発に委ねられてきました。
しかし今では、社員一人ひとりが学び続けられる環境を企業がどう設計できるかが、組織力を左右する重要なテーマになっています。
個人任せの学びは、どうしても一部の意識の高い人に偏りがちです。
そこで、社内研修やナレッジ共有を企業の“文化”として根づかせることができれば、誰もが自然に学び、教え合う風土が生まれます。
これは単なる教育制度の話ではなく、組織のカルチャーを再構築する取り組みといえます。
1-3.人的資本経営・心理的安全性・キャリア自律の文脈との関係性

近年注目を集めている「人的資本経営」の実現には、社員が自らのキャリアを主体的に考え、スキルを高め続けられる環境づくりが欠かせません。
また、「心理的安全性」が高い組織ほど、社員同士が気軽に質問し合い、知識を共有しやすくなります。
つまり、学びの仕組み化は単に教育の効率化を目的とするものではなく、「自律的なキャリア形成」や「信頼に基づくチームづくり」を支える土台にもなります。
1-4.教育を“継続的な投資”と捉える企業が増加
こうした流れを受け、近年は研修やナレッジ共有を「コスト」ではなく「投資」として捉える企業が増えています。
研修を一度限りにせず、日常業務の中で学びを循環させる仕組みを持つことで、社員のスキルアップにつながり、その結果、企業の競争力強化に直結します。
たとえばOJTの中に学びを組み込んだりするのも良いでしょう。
その他、ナレッジを社内ツールで蓄積・共有する取り組みや、社内コミュニティで成功事例を共有する文化づくりを行うなど、“継続学習”を前提とした人材育成戦略が大切です。
2.社内研修をしても効果がない場合の3つの理由
どれだけ丁寧に設計した社内研修でも、「実施したのに成果が感じられない」「結局、現場の行動が変わらない」という声は少なくありません。
その多くは、研修そのものの質よりも、学びを“どう活かすか”の仕組みに課題があります。ここでは、社内研修の効果が薄れてしまう主な3つの理由をご紹介します。
2-1.研修が「受けっぱなし」になっている
最もよくある課題が、研修を“受けて終わり”にしてしまうケースです。
受講直後はモチベーションが高くても、日々の業務に戻ると学んだ内容を実践する機会がないまま、時間とともに忘れられてしまうことが多くあります。
研修を行っても、フォローアップや実践の場がない状態では、知識は定着しません。
たとえば、研修後に「学びを現場で試す」「チーム内で共有する」「上司がフィードバックする」など、行動につなげる仕掛けが不可欠です。
研修はあくまで、“学びのプロセス”として捉えて、現場で成果につなげるにはどうすればいいかを設計し参加することが大切です。
2-2.研修内容が業務と結びついていない
受講者が「この内容は自分の仕事にどう関係するのか」が理解できないまま参加している場合は、学びは自分事化されません。
結果的に研修を受けたとしても、「やらされ感」が残り、行動変化にはつながりにくくなってしまいます。
研修を企画する際は、現場課題との接点を意識することが重要です。
例えば、実際の業務データや顧客事例を取り入れたり、職種別・階層別に内容をカスタマイズしたりすることで、学びがリアルな課題解決に直結しやすくなります。
“今の自分の仕事に役立つ”と実感できるかどうかが、研修効果を左右する分岐点です。
2-3.ナレッジが属人化してしまい、共有する仕組みがない
せっかく研修で良い知見が生まれても、それが特定の個人や部署に留まってしまうケースも少なくありません。
知識を得ても、共有する仕組みがないと、学びが“点”のままで終わってしまいます。
学びが組織全体に広がらなければ、同じ課題が繰り返されることになります。
せっかく人事部門や教育担当が、従業員のために研修を積み重ねたとしても知識が定着されないのは悲しいですよね。
近年では、ナレッジの共有の手段として社内SNSを活用し、研修の学びをチーム全体に展開する取り組みが増えています。
個人の経験を共有資産として蓄積することで、“学びの循環”が生まれ、組織全体の知的生産性が高まるといえます。
このように、研修効果を阻む要因は“研修そのもの”よりも、“その後の仕組み”で改善することが多いといえます。
次に、こうした課題を解決するための必要な、「学びを循環させる仕組み」のコツについてご紹介します。
3.より“学びが循環する組織”になる3つのステップ
「学びが定着しない」「研修効果が続かない」という課題を解決するためには、“学びを一方向で終わらせないこと”が重要です。
一人が得た知識を周囲に広げ、実践の中で磨き、再び組織に還元しましょう。循環が続くことで、個人の学びは組織の学びとなり組織力につながります。
ここでは、学びを循環させるための3つのステップをご紹介します。
3-1.インプット:誰でも学べる環境を整備する
まずは、社員が「いつでも・どこでも」学べる仕組みを整えることが第一歩です。
近年では、社内eラーニングや短尺動画、マイクロラーニングのようなスキマ時間でも学べる教育手法が広がっています。
紙の資料や集合研修に比べ、動画や事例ベースのコンテンツは理解度を高め、反復学習にも適しています。
また、単に教材を提供するだけでなく、新人から管理職まで階層別にナレッジを整理・可視化することも大切です。
誰がどの段階で何を学ぶべきかが明確になれば、学びが個人の努力ではなく、組織としての仕組みに変わります。
循環型の学びの“スタート地点”として、インプット環境を整えてみてはいかがでしょうか。
3-2.アウトプット:学びを共有・発信する場をつくる

学んだことを自分の中に留めず、他者に伝える・共有することで理解が深まります。
そのためには、「学びを共有する会」や「社内SNSでの学び投稿」など、アウトプットを仕組み化する仕組みが大切です。
例えば、
-
研修後に「実践してみたこと」を共有する情報共有の場を設ける
- 隔週でナレッジを共有する「ナレッジ共有」の場を設ける
-
月に一度、部署ごとに“成功事例発表会”を行う
-
チャットツール上に「#今日の学び」チャンネルをつくる
このような工夫を行うことで、学びの共有が“日常の習慣”になります。
ホープンでは、「ナレッジ共有会」という形式で、隔週に1回メンバーが2人ずつ、1回45分程度で知識を共有する勉強会の場を設けています。
各メンバーが持ち回りで登壇し、ナレッジを共有することで、個人の知識を組織で共有することで、組織力強化につながるよう取り組んでいます。
3-3.フィードバック:上司・チームで“実践の変化”を振り返る
学びを成果につなげるには、振り返りの仕組みも欠かせません。
例えば、1on1ミーティングやチームの定例会などで、「学び→行動→成果」の変化を一緒に確認することで、本人の気づきが深まり、学びが“定着”から“成長”へ発展します。
また、学びや成長の取り組みを評価指標の一部に組み込むことも効果的です。努力が正当に認められる仕組みを整えることで、学びへの意欲が継続しやすくなります。
フィードバックは単なる“振り返り”ではなく、次の成長サイクルを生み出す起点として捉え、振り返ることも大事にしましょう。
学びが循環する組織とは、研修や教育が、日常業務の一部になっている組織です。
インプット・アウトプット・フィードバックの3つのステップを継続的に回すことで、一人ひとりの成長を組織全体の力へと変えていきましょう。
4.ナレッジ共有を促進する取り組み事例
「学びの仕組み化」は、制度を整えるだけでなく、日々の業務にどう根づかせるかがカギです。
ここでは、その他ナレッジ共有の取り組み事例を4つご紹介します。取り組みやすいものから取り組んでみてはいかがでしょうか。
4-1.研修動画の整備
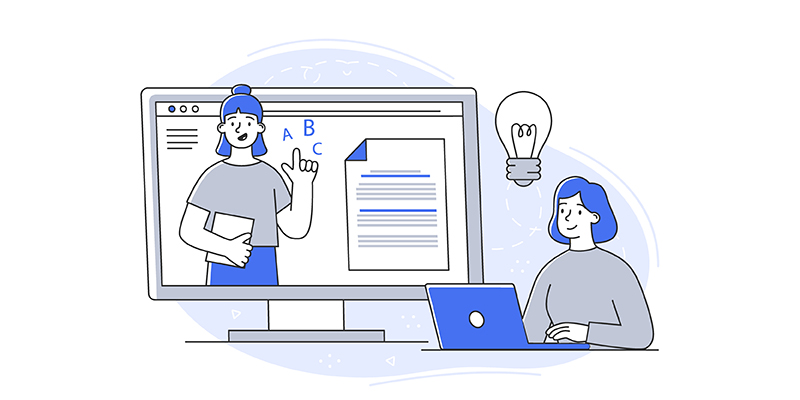
学びの“インプット環境”を整える取り組みとして、「研修動画」の整備があります。
例えば、社内のベテラン社員が持つノウハウを「研修動画」にすることで、教育の属人化を防ぐことにもつながります。
「研修動画」はライブラリー化し、社内ポータルで共有することで、新人や中途社員もいつでも見返せるようになります。
「動画」にしておくことで、繰り返し学べるため、知識の定着にもつながりやすくなります。
特に、現場で実際に起きたトラブル対応や、お客様への提案事例など、リアルな事例に基づいた動画は理解度が高く、集合研修よりも短時間で学べます。
「研修」を行うことは、社内講師(登壇者)の育成にもつながるため、学びの土台づくりとして研修動画を取り入れるのも選択肢です。
4-2.“学び報告”を週報に組み込む
次に、アウトプットを仕組み化した取り組みです。
学びの報告を定着させるため、週次の報告フォーマットに「今週の学び」という欄を設けることも選択肢の1つです。
社員が研修や日々の気づきを“自分の言葉で要約”して記入することで、内容が整理され学びの定着につなげることができます。
“言語化による定着”は、学びを深める効果が期待できます。
4-3.社内SNS×称賛文化の活用
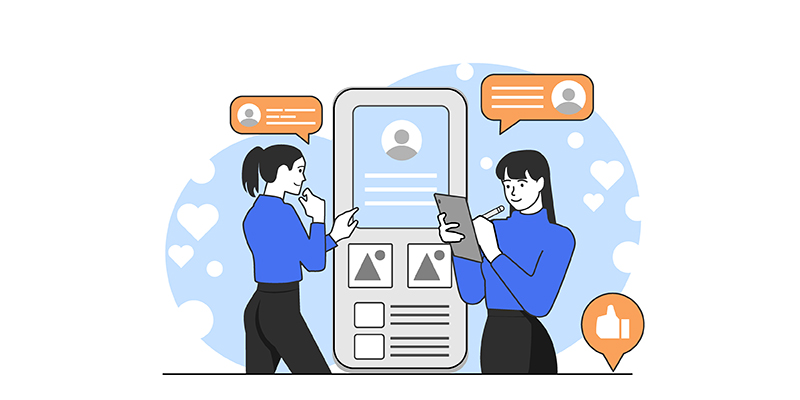
ナレッジ共有を文化として根づかせるために、社内SNSと称賛の仕組みを組み合わせることも有効です。
例えば、社員が学びを投稿する際に、他のメンバーが「いいね」や「Thanksコメント」を送ることで、日常の中で「誰かの学びが認められる」体験を積み重ねることができます。
また、社内SNS上で学びが可視化されることで、社員同士が自然に刺激を受け合い、「自分も共有してみよう」「次はこのテーマで発信してみたい」といったポジティブな循環を生むことも期待できます。
このような称賛文化は、「心理的安全性」を高め、学び合うか風土づくりにもつながります。
4-4.社内教育と採用広報の連動
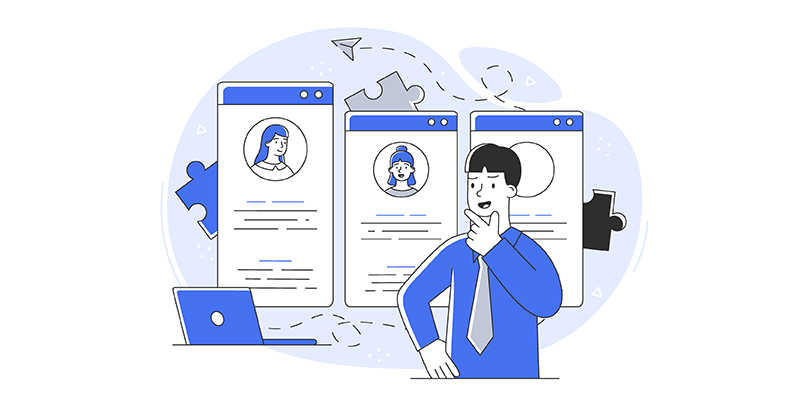
社内での学びの取り組みは、社外への発信にもつなげることができます。
たとえば、研修の様子や参加者インタビューを動画化し、採用サイトやSNSで発信することで、求職者に「社員の成長を支援してくれる会社」という印象を与えることができます。
このような取り組みは、成長意欲の高い人材の共感を呼び、採用ブランディングの強化にも効果的です。
さらに、社員自身が自分たちの学びや挑戦が外部に発信されることで、社内のモチベーション向上にもつながります。
社内教育の成果を社外発信へと広げることは、まさに“ナレッジ共有が企業価値を高める”という好循環を生み出す第一歩。
ぜひ、自社でも積極的に推進してみてはいかがでしょうか。
5.まとめ|学びを広げるためにできることから始めませんか?
社内の学びを定着させるには、“仕組み”化をすることが欠かせません。
また、学びは、研修の中だけで起きるものでもありません。日々の仕事や日常の中に気づきや発見があり、それを共有することで新しい価値が生まれます。
ぜひ継続的に活用できる教育コンテンツを整備し、ナレッジを組織の資産にするのはいかがでしょうか。
「誰かが学んだことが、誰かの成長につながる。」そんな連鎖が生まれたとき、学びは“仕組み”から“企業文化”へ変わります。
ホープンでは、教育を“文化”に変えるための社内コンテンツの制作を企画からサポートしております。
研修動画を始め、ナレッジブック・eラーニング動画の企画・制作・撮影のご支援など「学びが続く仕組み」をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。