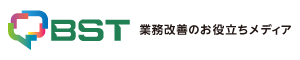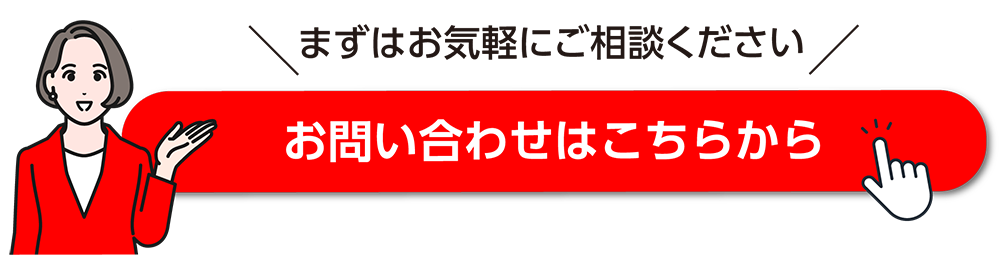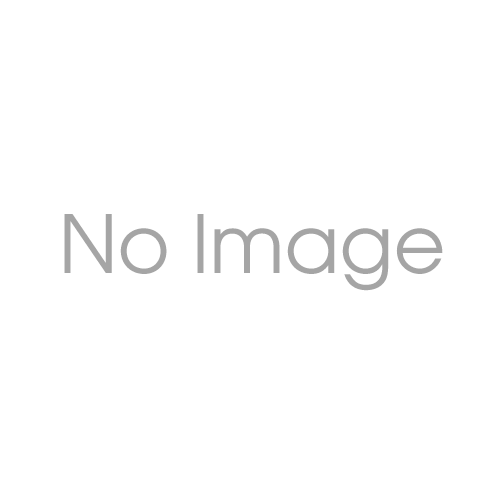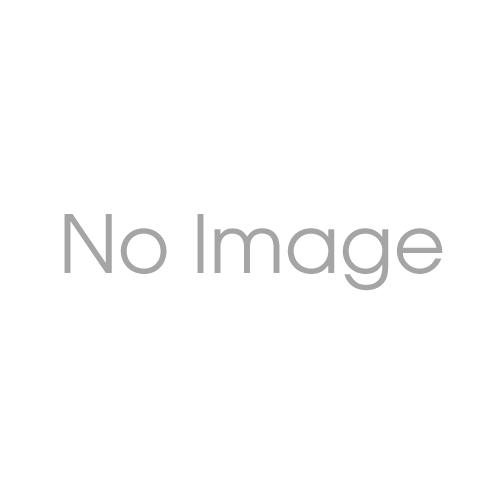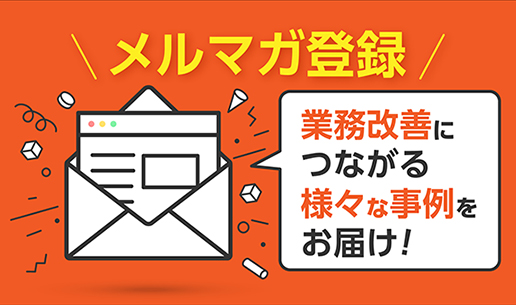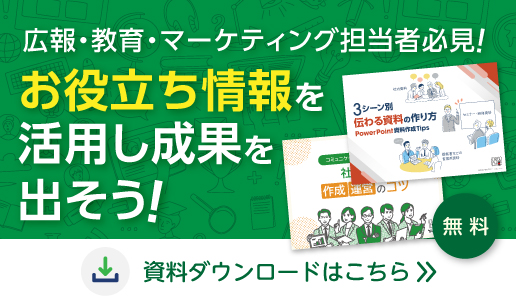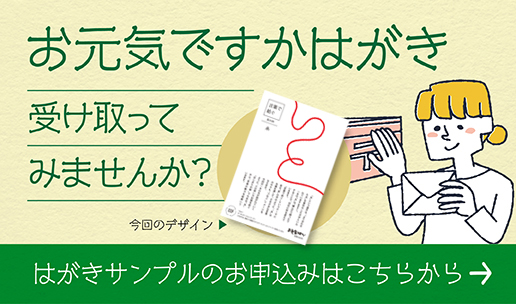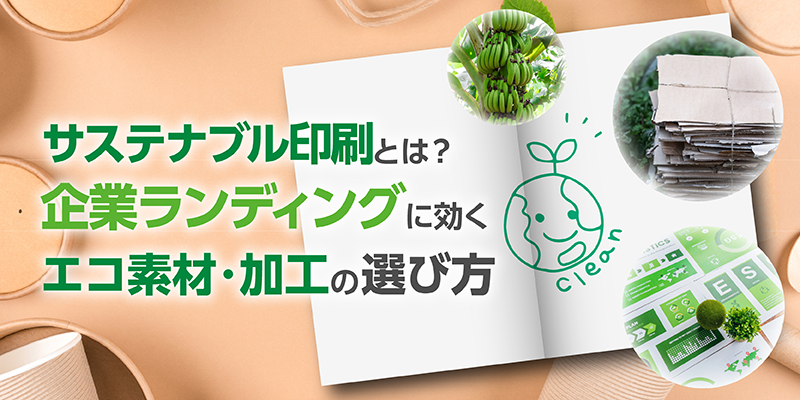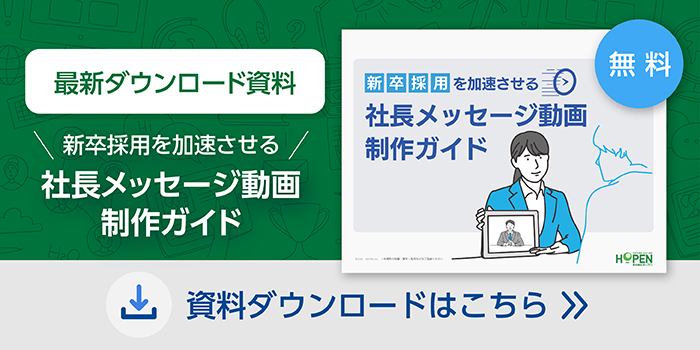オンラインイベントは、もはや一過性のコロナ対策ではなく、企業の「ブランディング」や「顧客接点の拡張」を担う重要な戦略手法として定着しました。セミナー・展示会・社内総会・採用イベントなど、あらゆるシーンでオンライン化が一般的になっていく中、「どんな内容なら参加者に響くのか」「リアルとの差別化はどう図るのか」といった悩みを抱える担当者も多いのではないでしょうか。
ただし実際の現場では、
「企画は良いのに、当日の進行が平坦だった」
「告知やアーカイブまで手が回らず、単発で終わった」
といった“企画止まり”の課題も少なくありません。
オンラインイベントを成果につなげるためには、企画だけでなく、「どう映像で見せるか」「どう残し、どう活かすか」までを含めた設計が大切です。
本記事では、オンラインイベントの意義を改めて整理しながら、目的別の最新企画例と成功のための設計ポイントを解説します。成果に繋げるヒントになればと思いますのでご覧ください。
◆目次
1.オンラインイベントの価値を再定義する
1-1.“代替”から“体験設計”へ
オンラインイベントは、もはや「リアルイベントの代替」ではなく、体験を設計する新たなステージになっています。
リアルでは制約となっていた、時間や距離、物理的な演出の限界を超え、デジタルならではの演出・参加体験を創り出せるようになりました。
例えば、複数の拠点を中継でつないで一体感を生む演出や、登壇者のコメントに合わせて資料が動的に展開されるインタラクティブ配信、また、チャットやリアクションを通じた即時の共感共有など、
単なる「情報提供」ではなく、視聴者が“参加者”として体験に没入する構造を生み出しています。
特に近年は、参加者一人ひとりに“パーソナルな体験”を設計する試みも増えています。
属性や行動履歴に応じて表示コンテンツを変えたり、AIがコメントや質問を要約してディスカッションに反映したりと、デジタル上でしか実現できない体験価値がブランドへの共感を高めています。
1-2.接点拡大とデータ活用の両立
オンラインイベントのもう一つの強みは、「接点の拡張」と「データ活用」を同時に実現できる点です。
物理的制約を超え、国内外・多拠点・リモートワーク環境下でも参加できることで、これまで接点を持てなかった層との新たな関係構築が可能になります。
さらに、デジタルプラットフォーム上で得られる、行動データの可視化により、マーケティングや人事施策における大きな武器になります。
視聴時間・離脱ポイント・チャット発言内容・アンケート結果などのデータを分析することで、
「どのコンテンツが最も関心を集めたか」「どのタイミングで反応が落ちたか」などを定量的に把握でき、次回の改善やリード育成に活かすことができます。
また、こうしたデータは単にイベント運営の指標にとどまらず、営業活動・採用広報・従業員エンゲージメント強化など、企業全体のコミュニケーション設計にも波及します。
オンラインイベントは、もはや一度きりの施策ではなく、「データを起点にした継続的な関係構築の場」として再定義されているのです。
2.目的別・オンラインイベントの最新企画例

オンラインイベントは、目的に応じて形を変えながら、さまざまなフェーズで企業活動を支えています。
ここでは、社内コミュニケーションの強化/顧客・潜在層へのブランド浸透/採用力の向上という3つの目的別に、最新の企画事例とその意図を紹介します。
2-1.社内向けイベント|“共体験”でエンゲージメントを高める
リモートワークも定着した中で、「社員が同じ時間に、同じ体験を共有する」機会は貴重になりました。
そんな中、オンラインイベントは、距離や役職の壁を超えた“共体験”を生み、組織の一体感を高めることができます。
-
ハイブリッド社員総会
現地会場とオンラインを同時開催し、全国・海外の拠点をつなぐ形が主流になっています。
登壇者の発言に合わせてリアルタイム投票やコメントを反映させることで、「見る会」から「参加する総会」へと変化します。 -
オンライン表彰式・アワード
社内功績を称える場を映像演出でドラマチックに仕立てるケースが増加しています。
受賞者紹介ムービーやサプライズ映像を組み合わせることで、個人の貢献を可視化し、企業文化の浸透にもつながります。 -
バーチャル社員旅行・チームビルディング
オンライン旅行、リモートクッキング、謎解きイベントなど、非日常体験を通じて“つながり”を再構築する企画が人気です。
部署横断での交流促進や、社内SNSとの連動による継続的なコミュニケーションにも波及します。
例えば、
・イベント冒頭で使用するオープニング動画
・受賞者や登壇者を紹介する事前インタビュー映像
・イベント後に共有するダイジェスト動画
といった映像を組み合わせることで、一度きりの体験を社内全体へ波及させることができます。
また、映像として残すことで、当日参加できなかった社員への共有や、社内研修・理念浸透コンテンツとしての二次活用も可能になります。
社内イベントを「やって終わり」にせず、企業文化として蓄積していくためにも、映像活用を前提とした設計が有効です。
2-2.社外向けイベント|ブランド価値を体験で伝える
マーケティング施策としてのオンラインイベントは、「ブランドの世界観をどう体験として設計するか」が成功の鍵です。情報提供ではなく、企業の想い・製品の背景・社会的価値を“感じさせる”体験設計が求められます。
-
オンライン展示会・新製品発表会
3D空間やバーチャルブースを活用し、製品を触れるように見せる演出ができます。
ダウンロード導線やチャット商談を設計すれば、リード獲得と購買意欲喚起を同時に実現できます。 -
ブランド体験型ウェビナー
専門家講演と「ストーリーテリング」を融合し、製品の“背景”や“開発者の想い”を伝える形式です。
単なる知識提供ではなく、共感を促す物語設計が大切です。 -
オンラインツアー・体験型イベント
地域や業界の強みを活かし、五感に訴える体験をデジタル上で再現します。
たとえば食品メーカーなら“事前サンプル×リアルタイム試食”、観光業なら“現地中継+お土産配送”など、「家の中でブランドを体験する仕掛け」がファン化につながります。
告知段階では、イベントの世界観や背景を伝える短尺動画を活用することで、参加前からブランド理解を促すことができます。
当日は、オープニング動画によってメッセージの軸を共有し、イベント全体の文脈を整えることで、視聴者の没入感を高めることができます。
さらに、イベント後には、要点を整理したアーカイブ編集やダイジェスト動画を制作することで、営業資料・Webコンテンツ・SNSなどへ展開でき、イベントを起点とした継続的な接点づくりが可能です。
ブランド価値を体験として伝えるためには、こうした映像を軸にした一貫した設計が欠かせません。
2-3.採用・リクルート関連イベント|“企業理解”を可視化する
採用活動におけるオンラインイベントは、候補者に「働くイメージ」を持たせる“理解促進装置”です。リアルよりも心理的ハードルが低く、候補者と企業の距離を自然に縮めることができます。
-
バーチャル会社訪問/職場ライブツアー
実際のオフィスや現場を中継し、働く人の声や雰囲気をそのまま伝えるコンテンツ。
「雰囲気がわかる」「自分が働く姿を想像できた」という声が多く、応募意欲の向上に直結します。 -
オンライン座談会・キャリアトークセッション
若手社員×採用担当×経営層など複数の視点を交差させ、
リアルな社風・キャリアパスを共有することで、“選ばれる企業”へと印象を強化。
匿名質問機能やリアルタイムQ&Aで、候補者の不安解消にもつながります。 -
オンデマンド型説明会・採用動画シリーズ
「いつでも視聴できる」「スマホで短時間に理解できる」フォーマットは、
時間的制約のある学生・転職者層に特に有効。
再生データを分析し、次回コンテンツに反映するデータドリブン採用広報も定着しています。
そのため、
・会社の価値観を伝えるオープニング動画
・社員インタビューや1日の仕事紹介映像
・オンデマンドで視聴できる説明動画
などを組み合わせることで、イベント前後の企業理解を大きく高めることができます。
特に、オンデマンド動画を用意しておくことで、イベント参加前の予習や、参加後の振り返りにも活用でき、応募率や面談希望率の向上につながります。
採用イベントを単発の説明会で終わらせず、継続的な採用広報コンテンツとして機能させるためにも、映像活用を前提とした設計が有効です。
●ポイント:オンラインイベントは“単発施策”ではなく“関係構築の循環”へ
オンラインイベントの本質は、「一度の配信で終わらせないこと」です。
アーカイブ配信やダイジェスト動画化、SNSでの再活用など、イベントを起点にしたコミュニティ形成・リード育成サイクルを設計することで、成果は長期化します。
3. オンラインイベントを成功させる「動画活用設計」の考え方
オンラインイベントを成功させるためには、単発の映像制作ではなく、イベント全体を貫く「動画活用設計」が重要です。
代表的な構成は、以下の3点が有効です。
告知動画
イベントの目的・魅力を端的に伝え、参加意欲を高めます
オープニング動画
当日の冒頭で使用し、世界観と集中力を一気に引き上げる
アーカイブ・編集動画
イベント後に要点を整理し、営業・採用・広報へ展開しましょう
この3点をセットで設計することで、オンラインイベントは“一度きり”ではなく、企業のコンテンツ資産として機能します。
3. 成功するオンラインイベントの設計ポイント
4. 成功するオンラインイベントの設計ポイント
オンラインイベントの成果を分けるのは、企画や演出の派手さではなく、「目的に基づいた体験設計」と「データに裏づけられた改善サイクル」です。
ここでは、参加者の満足と成果の両立を実現するための3つのポイントを紹介します。
4-1. 目的とKPIの明確化

まず最も重要なのは、「なぜ開催するのか」「何をもって成功とするのか」を定義することです。
目的が曖昧なまま企画を進めると、演出や内容の方向性がぶれ、結果として“印象には残るが成果が出ないイベント”になりかねません。
目的は大きく以下3つに分類できます。
-
社内向け(インナー)
エンゲージメント向上、離職防止、理念浸透 → KPI例:アンケート満足度、コメント投稿率、社員SNSでの共有数 -
社外向け(マーケティング)
リード獲得、ブランド認知、商談化率向上 → KPI例:申込者数、視聴完了率、資料DL・問い合わせ件数、営業転換率 -
採用向け(リクルート)
応募率、説明会満足度、内定承諾率改善 → KPI例:参加後の応募率、面談希望数、動画視聴データ分析による関心分布
このように、各段階や対象によって「どんな感情を動かしたいのか」「どんな行動を生みたいのか」を数値化することが、企画の方向性を定める最初のステップです。
また、オンラインイベントは“データが残る”という大きな特徴を持ちます。
リアルイベントでは測定できなかった「離脱ポイント」「視聴時間」「反応率」をデータとして可視化し、次のイベントやマーケティング施策に生かすことが可能です。
4-2. 双方向性・体験価値の設計
オンラインイベントが成功するかどうかは、「参加者がどれだけ自分ごと化できるか」にかかっています。
一方通行の配信では集中が続かず、記憶にも残りません。
効果的なのは、以下のような双方向コミュニケーションの設計です。
-
リアルタイム投票・クイズ
講演やプレゼン中に「あなたはどちら派?」と問いかけ、結果を即座に可視化することで、
参加者に“自分もイベントの一部”である感覚を与えます。 -
チャット・コメント機能
司会者や登壇者がリアルタイムで拾うことで、会場の“空気感”をオンラインでも再現。
心理的距離を縮める演出が、エンゲージメント向上につながります。 -
ブレイクアウトルーム・小規模交流
特にBtoBや採用イベントでは、少人数での意見交換が有効。
参加者の声を聞く時間を設けることで、「参加してよかった」という体験の余韻を残すことができます。
さらに近年は、ゲーミフィケーションを取り入れる事例も増加中です。
得点制やスタンプラリー形式で参加を促すことで、飽きさせず、より能動的な関与を引き出すことができます。
4-3. アーカイブ&二次活用
オンラインイベントの魅力は、“その瞬間で終わらない”ことです。
リアルイベントでは再現できなかったコンテンツの再利用・拡張が、長期的なリード育成・社内教育・ブランディング強化に直結します。
-
オンデマンド配信
当日参加できなかった層にもリーチでき、再生データから関心領域を分析可能。
「視聴完了率が高いテーマ」を抽出し、次の企画や営業資料に反映できます。 -
ショート動画・ダイジェスト化
印象的な発言や事例を30〜60秒にまとめ、SNSで拡散することで、
イベントが終わった後もブランド発信を継続できます。 -
ナレッジ化・社内研修コンテンツとして再利用
社内イベントやセミナーの内容をストックし、学習コンテンツ化することで、
人的資本経営の観点からも資産化が可能です。
こうした“二次活用前提”の設計を行うことで、一度のイベントが 「終わるコンテンツ」から「育つコンテンツ」 へと変わります。
オンラインイベントは、“届ける”から“共に創る”にすることで、参加者の体験価値を中心に据え、データを活用しながら改善を重ねることができます。
そうすることで、一過性の施策ではなく、企業と人をつなぐ持続的なブランド接点になります。
5. 企画段階で押さえるべき実務ポイント
オンラインイベントの成否は、「当日の演出」ではなく「企画段階の準備精度」で決まります。
どれだけ良い企画でも、運営体制やシナリオ、技術面の設計が甘ければ、参加者体験が損なわれ、ブランド価値の毀損につながりかねません。
ここでは、スムーズで成果の出るオンラインイベントを実現するための実務ポイントを解説します。
5-1. 社内の関係部署との早期連携
オンラインイベントは、「情報・技術・発信」すべてを横断するプロジェクトです。
そのため、企画初期の段階から以下の部署との連携を図ることが重要です。
-
人事/総務部門
社内イベントや採用系での出演者・参加者調整 -
広報/マーケティング部門
外部への発信設計・ブランドトーンの統一 -
営業/カスタマーサクセス部門
リード活用・商談転換設計 -
情報システム/IT部門
配信環境やセキュリティ面の確認
これらの部署と“早めに合意形成”を行うことで、後工程の修正コストを大幅に削減できます。
また、関係部署を巻き込んで「誰に・何を・どう伝えるか」を共通認識化することが、結果としてメッセージの一貫性とブランド体験の統一感につながります。
5-2. シナリオ設計は「集中時間」と「体験リズム」を意識
オンライン視聴者の集中力は、一般的に20〜30分が限界といわれています。
長時間の講演形式では離脱率が高まりやすく、構成段階で「リズム」を設計することが成功の鍵となります。
具体的には以下に気を付けて設計するようにしましょう。
-
前半(導入)
興味を引くストーリーや映像で惹きつける -
中盤(本編)
データ・事例・ゲストトークなどで深掘り -
後半(まとめ)
行動喚起(資料DL・問い合わせ・応募)を明確に提示
さらに、シナリオと進行台本を分けて設計することで、登壇者の話すテンポ・映像の切り替え・チャット導入タイミングを正確に制御できます。
また、プロのディレクターを交えた「演出設計」を取り入れるることで、全体のテンポと没入感の向上が期待できます。
5-3. 技術リハーサル・機材テストの徹底

オンラインイベントで最も多いトラブルは、「音声・映像・通信の不具合」です。どんなに優れたコンテンツでも、技術的な不備があると信頼性を損なってしまいます。
そうならないために、以下のように段階的なリハーサルを行うようにしましょう。
-
一次テスト
使用ツール(Zoom/Teams/Webex等)の接続・設定確認 -
二次テスト
実際の登壇者・機材を用いた音声・照明・画角チェック -
最終リハーサル
全員参加で本番同様に通し進行、トラブル対応フロー確認
特に登壇者が外部の場合、環境の違い(照明・通信速度・マイク品質)により印象が大きく左右されます。
事前に「登壇マニュアル」「推奨デバイスリスト」を共有しておくことで、品質のばらつきを防げます。
5-4. アフターフォロー設計で「イベントを終わらせない」
オンラインイベントは、アフターフォローが肝です。イベントを開催して達成感で満足してしまいがちですが、「終了後のフォローアップ」をしっかり行うようにしましょう。
参加直後は関心度が高いため、次のアクションを設計することが重要です。
-
アンケート配信
満足度や興味テーマを把握し、次回企画・営業活動へ反映 -
サンクスメール
感謝+再視聴リンクや関連資料DLを案内し、体験を再接続 -
SNS・Webでのハイライト公開
イベントの余韻を活かしたブランド露出 -
次回告知・継続イベント案内
ファン層形成とリード育成のサイクル化
特に、アンケート結果と視聴ログを掛け合わせると、「誰がどの内容に興味を持ったか」というデータを抽出でき、イベントをきっかけとした継続的なコミュニケーション設計が可能になります。
6. 成功への近道は「プロとの共創」

オンラインイベントは、企画・演出・配信・分析のすべてが噛み合ってこそ成功します。しかし、企画・進行・映像・配信・分析を、社内だけで最適解を出すのは簡単ではありません。
特に、
・イベント全体の構成と映像の役割設計
・当日進行と演出のバランス
・アーカイブや二次活用まで見据えた編集
は、専門的な視点が成果を大きく左右します。
オンラインイベントの成功には、外部のパートナーと連携することも大切です。そうすることで、視聴者体験の質と運営の安定性を両立することができます。
ホープンは、50年以上にわたり撮影から動画制作まで、お客様のセミナーや展示会などのイベント支援、研修サポートを行ってまいりました。
そのため、当日のイベントのサポートにあたり撮影のご支援も可能です。また、撮影にあたりホープンのスタジオ「ICHIGO ICHIE DIGITAL」もご活用いただけます。
当日は、ホープンの撮影チームが、撮影のディレクションから音声面もサポートいたします。
オンラインイベントを「ブランド体験の場」として戦略的に活用したいけど、リソースが足りない…。
自社だけでの実施は不安…。などお悩みをお持ちの場合は、ぜひホープンにお気軽にご相談ください。