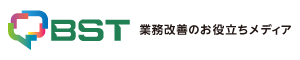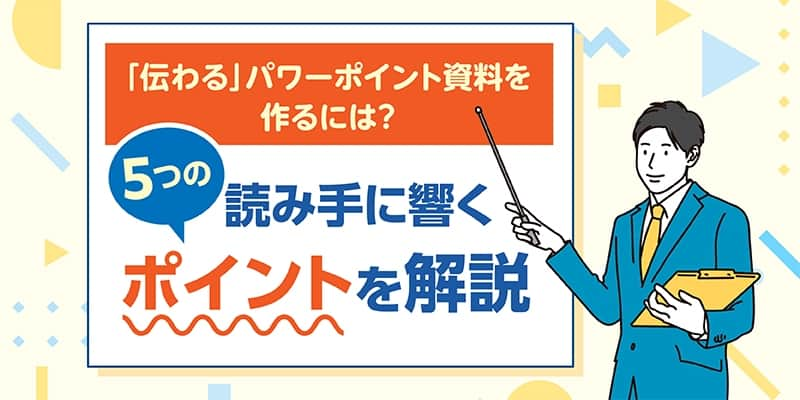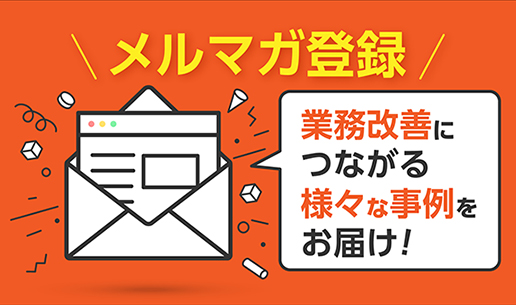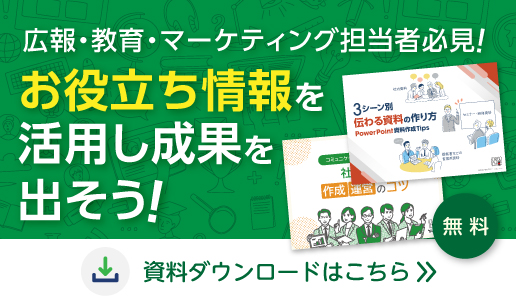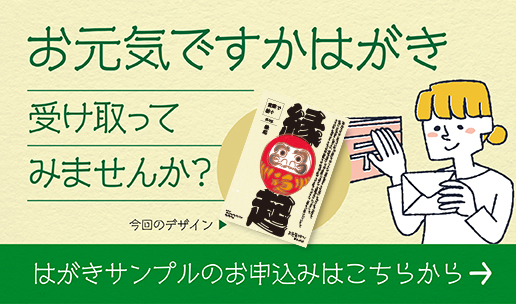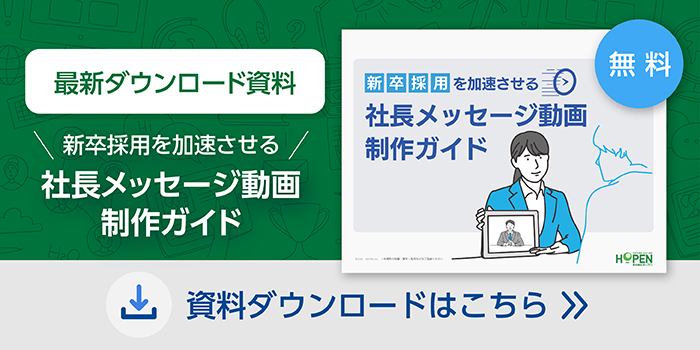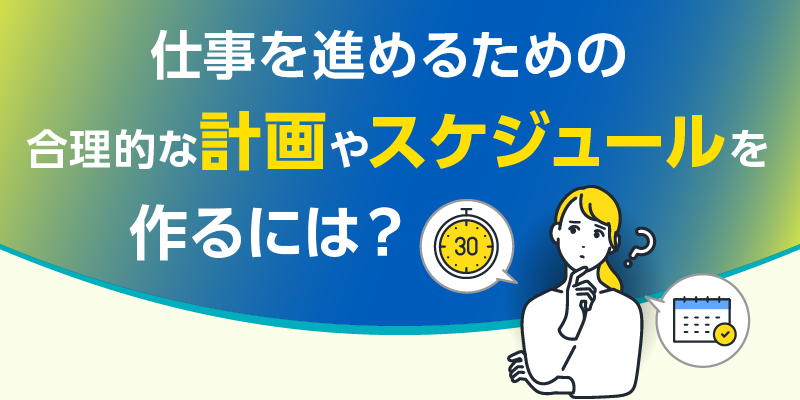
リモートワークやオンライン会議の増加により、日々の業務はますます複雑化しています。
「打ち合わせが多くて資料作成が追いつかない…。」「予定通りに進まない…。」と感じたことはありませんか?
そんな今こそ求められるのが、“変化に強い計画力”です。
今回は、企画・営業・管理職など非定型業務を多く抱える方に向けて、合理的に仕事を進めるための「計画の立て方」や「外部委託の上手な使い方」について解説いたします。
◆目次
1.なぜ計画が必要なのか?「勢い」よりも「見通し」で動くことの大切さ

日々の仕事には、ひとりで完結できる作業から、複数の部署・関係先と連携しながら進める大規模なプロジェクトまで、さまざまな種類があります。
どんな仕事であっても、成果を安定的に出し続けるためには、「その場の勢い」ではなく、「先を見通して動く力」が欠かせません。
計画を立てることは、単に予定を立てるということではありません。
「何を目的に、どの順序で、どのように進めるか」を考えることで、仕事を整理し、全体をコントロールできるようになります。
それでは、計画を立てることで得られる具体的なメリットをご紹介します。
メリット1:仕事全体を俯瞰し、優先順位をつけることができる
目の前のタスクをひとつずつ片づけていくだけでは、気づけば本来注力すべき業務が後回しになっていた―そんな経験はありませんか?
計画を立てることで、すべてのタスクを「全体像の中での位置づけ」として把握できるようになります。
「今、どの仕事が最も成果に直結するのか」「どれを後回しにしても問題ないのか」が明確になることで、限られた時間とリソースを戦略的に使うことができます。
メリット2:関係者とスムーズに調整できるようになる
複数人で関わるプロジェクトでは、関係者それぞれのスケジュールや優先順位が異なります。
先に計画を立てておくことで、「この日までにここまで進めたい」「次の打ち合わせではこの点を決めたい」といった具体的な見通しを共有できるため、チーム内での調整がスムーズになります。
特に、リモートワークのように非対面で進む業務の場合は、特に「共有された計画」が重要です。事前に計画を共有することで、チーム全体の足並みをそろえることができます。
メリット3:想定外の事態にも柔軟に対応することができる
「急な会議」「想定外の修正依頼」「関係者のスケジュール変更」など、仕事には突発的な出来事がつきものです。
先に、計画を立てておくことで、進行状況を把握しやすくなり、どこにどれだけ余裕があるのか、どの工程を後ろ倒しできるのか…といった判断ができるようになります。
つまり、先に計画をしておくことは“柔軟に動くための土台”となり、変化に強い人ほど、実は綿密な計画を持っています。
メリット4:タスクの抜け漏れを防ぐことで安心して進めることができる
複数案件を同時に進行していると、「どこまで終わったか」「誰に確認を依頼したか」が曖昧になりがちです。
そういった場合にも、事前に計画を立てておくことで、タスクの抜け漏れを防ぎ、ミスや手戻りを減らすことができます。
また、スケジュール通りに進んでいるという安心感が得られ、精神的にも余裕を持って仕事に向き合うことができます。
メリット5:もはや計画力=“信頼される人”に共通するスキル
「計画力」は、単なる効率化のテクニックではなく、「信頼される人」の共通スキルです。
上司やクライアントから見て、「この人は先を見て動ける」「任せても安心」と感じさせるのは、「計画に基づいて仕事を進める姿勢」です。
綿密な計画をしておくことで、トラブルが起きたときにも冷静に説明・対処ができ、結果的にチームや顧客からの信頼を積み重ねていくことにつながります。
計画を立てること=「今の自分」が“未来の自分”のために道筋を作っておくことです。
スケジュールを立てることは、単なる「予定管理」ではなく、「成果を出し続ける仕組みづくり」になるため、ぜひ計画を立てて進めるようにしておきましょう。
2.計画は「変化に備えるための地図」にもなる
「計画を立ててもその通りにならない」「どうせ予定は崩れるから意味がない」など、そう感じた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
しかし、実はこの考え方こそが“計画を誤解している状態”です。
本来、計画とは「未来を正確に予測するためのもの」ではなく、変化を前提に備えるための“地図”のようなものです。
ゴールまでのルートを示す地図があれば、道に迷っても現在地を確認し、別の道を探すことができます。
これは、仕事も同じで、計画を持っていることで、想定外の出来事が起きても修正・対応をスムーズ行うことができます。
2-1.「計画通りにいかない」こともあるということも考慮しておく
事前に計画を立てていても、ビジネスの現場では、思い描いたスケジュール通りに進むことの方が少ないものです。
当初想定していなかった、突然の打ち合わせ、お客様の要望の変更、社内の確認待ちなど、どれも自分ではコントロールしにくい外的要因によって、予定は簡単に変わってしまいます。
だからこそ、計画を立てる際には「変化を織り込んだ計画」を作っておくことが大切です。
例えば、
-
納期に対して1〜2日の余裕を設ける
-
優先順位をA・B・Cに分類して、B・Cは柔軟に動かせるようにする
-
タスクを「今週中」「来週以降」など、大まかに整理しておく
このような“余白のある計画”ももっておくことで、想定外の変更が起きても慌てずに対応することができます。
2-2.計画があることで「焦らずに判断できる」
突発的な仕事が入ると、多くの人は「何から手をつけるべきか」がわからなくなり、焦りやストレスを感じてしまいます。
しかし、事前に計画があれば、全体のタスクと進捗を把握できるため、「どこにどれだけ時間を割けるか」「何を後回しにできるか」を判断することができます。
その結果、感情的な焦りに左右されずに、冷静に優先順位を見極めることができるのです。
特に、マネージャーやリーダー職にとって「計画力」は重要なスキルであり、チームの生産性を左右する“判断の質”を高める要因にもなります。
2-3.計画は「他者との信頼を保つツール」
リモートワークが進む現代では、チームメンバーの作業状況が見えにくくなっています。
そのため、口頭での報告よりも「いつまでに、どこまで進めるか」という計画そのものが、信頼を築く材料になります。
例えば、
「今週中にドラフトを提出します」
「木曜までに上司確認を完了させます」
といった具体的な計画を示すだけでも、相手は安心し、進捗共有がスムーズになります。
つまり計画は、自分の作業管理ツールであると同時に、チーム全体の信頼関係を保つコミュニケーションツールにもなるのです。
計画があるからこそ、予定変更にも冷静に対応でき、他者との連携もスムーズになります。
「見通しを持って動ける人」=「信頼される人」となり、計画とは、変化を恐れず進むための最も強力な武器になります。
3.実行できる計画を作る3つのステップ

「計画を立てたけれど、結局うまくいかなかった」
「スケジュールは作ったのに、現場でまったく機能していない」
そんな経験は誰にでもありますよね。実は、“計画を立てること”と“実行できる計画を立てること”は、まったく別物なのはご存じでしょうか。
ここでは、計画を「絵に描いた餅」で終わらせず、成果につながる“実行可能な設計”に変えるための、3つのステップをご紹介します。
3-1.3つの基本要素を明確にする
計画の骨格をつくる要素は、次の3つに整理されます。
-
目的(なぜやるのか)
-
目標(どんな状態を成功とするのか)
-
期限(いつまでに達成するのか)
この3つがそろわないまま進めてしまうと、途中で方向性を見失ったり、「何をもって完了とするのか」が曖昧なままタスクだけが増えてしまいます。
例えば、営業担当の場合はこのように明確にておきましょう。
-
目的:新サービスの販売拡大
-
目標:3か月以内に新規顧客100件の受注
-
期限:四半期末まで
このように、目的・目標・期限をセットにして設定することで、何を優先すべきかが明確になります。
目的が「成果の方向性」、目標が「数値的なゴール」、期限が「行動のリズム」をつくり、どれかひとつが欠けても計画は機能しません。
計画づくりの最初の段階は、「この仕事は何のために存在しているのか?」を、一度言葉にしてみると、それだけでタスクの重みづけができ、自然に整理することができます。
3-2.目的に合わせて「3段階の計画」を使い分ける
計画を立てるときに、多くの人が「一枚のスケジュール表」で全てを管理しようとしますが、実際には目的や範囲によって、求められる粒度や視点が異なります。
そこで意識したいのが、次の「3段階の計画」です。計画をする際には、目的に合わせて3段階で計画をするとスムーズに立てることができます。
(1)全体を把握するための計画(中長期・マクロ視点)
これは、会社や部門、プロジェクト全体を俯瞰して「どの時期に何を行うか」を整理する計画です。
たとえば、年間目標を達成するために「上期は認知向上」「下期は成約強化」というように、時間軸で重点テーマを決めていきましょう。
プロジェクト単位では、「案件Aを4〜10月」「案件Bを5〜10月」といった形で、複数案件の時期を重ねて見える化するのも有効です。
これにより、チーム内でリソースが重なる時期や、外部発注のタイミングなどを早めに把握することができます。
(2)手順を把握するための計画(中期・プロジェクト単位)
次に必要なのが、目標を達成するまでの工程を細かく分解する“手順の設計”です。
例えば、オンラインセミナーの開催であれば、「テーマ決定 → 講師調整 → 台本作成 → スライドデザイン → 集客 → 本番 → 事後アンケート」というように流れを段階的に整理するようにしましょう。
この段階で重要なのは、「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確にしておくことです。
ここを曖昧にすると、進行中に責任の所在があいまいになり、スケジュールが遅れやすくなるので注意しましょう。
また、手順計画を立てるときは、各タスクを「完了条件」で書くようにすることがおすすめです。
「資料を作る」ではなく、「資料をレビューに出せる状態にする」と、具体化することで、行動が明確になるだけでなく質も上がります。
(3)時間を管理するための計画(短期・日単位)
最後に、日々のスケジュールやタスクを組み立てる“ミクロ視点”の計画です。
これは、実際に1日の流れを決めるための最も現場的な計画になります。
例えば、
-
9:00〜9:30 メールチェック・日報確認
-
9:30〜10:30 チーム定例会議
-
10:30〜12:00 A案件の提案資料作成
-
13:00〜14:00 顧客B社とのオンライン打ち合わせ
-
15:00〜17:00 新規案件の調査・まとめ
このように、1日をブロック単位で区切ると、集中すべき時間と切り替える時間のリズムが生まれます。
また、余白として10〜15%程度残しておくと、突発的な対応にも柔軟に動くことができます。
3-3.「自分でやる」と「任せる」を見極める
計画を立てると、「やるべきこと」はどんどん出てきますが、全てを自分で抱え込むのは現実的ではありません。
限られた時間とリソースの中で成果を最大化するには、“どこまで自分で行い、どこからを任せるか”の判断が必要不可欠です。
任せる際の判断基準としては、次の3つを意識するのがおすすめです。
-
その仕事は自社の競争力や価値に直結する“コア業務”か?
-
将来的に社内にノウハウを残す必要があるか?
-
外部に任せた方が、スピード・品質・コストの面で合理的か?
たとえば、プレゼン資料のデザインやセミナー運営などは、専門知識や作業時間を要する領域です。
こうした業務を外部に委託することで、社内メンバーは“戦略や意思決定”といった本質的な仕事に集中することができます。
「全部自分でやる」ことが頑張りではなく、「任せる判断ができる」ことがリーダーシップです。
効率的に成果を出すチームほど、この線引きが明確になっています。
4.外部委託の活用で「計画の実現力」を高める
どれほど綿密に計画を立てても、実行段階で「人手が足りない」「納期が厳しい」「品質を担保できない」といった壁にぶつかることは少なくありません。
そこでポイントになるのは、計画を“実現可能なもの”に変えるために、社内リソースだけで完結させようとせず、外部パートナーの力を戦略的に取り入れる発想です。
外部委託(BPO=Business Process Outsourcing)は、単なる業務代行ではありません。
企業が「やるべき仕事」と「任せるべき仕事」を切り分け、リソースを最適に配分するための選択肢の一つです。
4-1.外部委託がもたらす3つの実践的メリット

外部委託を上手に活用することで、次のようなメリットがあります。
-
納期遅延のリスクを減らし、安定した進行が可能になる
プロジェクトが計画通りに進まない最大の原因は、リソースの逼迫です。
社内メンバーの業務量が限界に達した状態で新しい案件が入ると、
スケジュール遅延や品質低下が連鎖的に発生します。
そこで、資料作成やデザインなどのノンコア業務を外部に委託することで、
社内はコア業務に集中でき、全体の進行が安定します。
結果として、計画を“予定通りに完遂できるチーム体制”が整うのです。 -
専門チームのノウハウを活かし、品質を高めることができる
社内にはない専門知識や経験を外部のプロフェッショナルが補うことで、
成果物の質を飛躍的に高めることができます。
たとえば、資料作成を得意とするデザイナーに依頼すれば、
内容の伝わりやすさやビジュアル表現の精度が格段に上がり、
結果としてプレゼンテーションや商談の成果も向上します。
つまり、**外部委託は「スピードのための手段」だけでなく、「品質向上のための戦略」**でもあります。 -
社員の作業負担を減らし、創造的な業務に時間を使える
ルーチンワークや定型的な業務を外部に任せることで、
社員は「考える仕事」「付加価値を生む仕事」に専念できるようになります。
特に企画・営業・広報など、発想や提案が求められる職種ほど、
作業時間を削減できるかどうかが成果を左右します。
BPOを導入することは、“人の時間”という限られた資源を、より戦略的に使う投資なのです。
4-2.「任せる」ことは、“手放す”ことではない
外部委託に抵抗を感じる方は、「社内の統制が取れなくなるのでは?」という不安を抱くのではないでしょうか。
しかし、BPOの本質は“手放す”ことではなく、“設計を委ねる”ことです。
自社が「何を任せ、どの範囲をコントロールするか」を明確にした上で委託をすることで、むしろ全体像の見通しが立ちやすくなり、計画の管理精度は上がります。
重要なのは、
-
業務範囲と目的を明文化すること
-
成果物や納期の定義を共有すること
-
進行中の確認・レビューを定期的に行うこと
この3点を押さえることで、外部委託は「不安要素」ではなく、“計画実現の推進エンジン”になります。
4-3.“見せ方が成果を左右する仕事”ほどプロに任せよう
オンラインセミナーやプレゼン資料など、「視覚的な印象」や「構成のわかりやすさ」が成果を左右する仕事では、デザインや資料構成のプロフェッショナルを活用する価値は非常に高いといえます。
-
内容は良いのに、スライドのデザインで説得力が半減してしまう
-
話したいことが多すぎて、構成がまとまらない
-
ウェビナー後のアンケート回収や事務作業に時間を取られてしまう
このような課題は、外部への委託がおすすめです。
デザインなどはプロに任せることで、「伝わる構成」「魅せるデザイン」「効率的な運営」を同時に実現でき、社内メンバーは本来の目的である「伝える」「成果を出す」ことに集中することができます。
4-4.“外部を味方につける”ことで、“計画”が推進され組織を進化させる
計画を立てても実行できないチームがある場合は、たいてい“自分たちだけで何とかしよう”と抱え込みがちです。
一方で、成果を出し続ける組織は、「自社にしかできない仕事」と「外部と協働すべき仕事」を明確に線引きし、社外のリソースを“共に計画を進めるパートナー”として取り入れています。
「外部委託」とは「自社でできないことを他人に頼む手段」ではなく、“より高い計画精度で成果を実現するための組織戦略”として捉え取り入れています。
どんなに優れた計画を立てても、実行できなければ「絵にかいた餅」になり意味がありません。
自社で難しいのであれば、外部の力も柔軟に取り入れ、計画を現実的な行動に変える仕組みを持つようにしましょう。
5. まとめ|計画の遂行にあたり外部も味方につけよう

計画を立てることは、単なる「予定づくり」ではありません。自分とチームが迷わずに前へ進むための“指針”をつくることです。
世の中の状況も、業務の環境も、日々変化しているため、最初から完璧な計画を立てようとするのではなく、変化を前提にしながら、柔軟に再設計できる計画を持つようにしましょう。
また、計画をしたら「絵にかいた餅」になってしまわなぬよう、自社がやるべきことと外部に任せるべきことを正しく見極めるのも大切です。
そうすることで、チーム全体の負荷を減らし、限られたリソースを最大限に活かすことができます。
ホープンは、印刷からWeb制作、動画制作まで、お客様のコンテンツ制作をサポートしております。
お客様が立てた計画に合わせて達成できるよう、伝わるツール制作をご支援しておりますのでお気軽にご相談ください。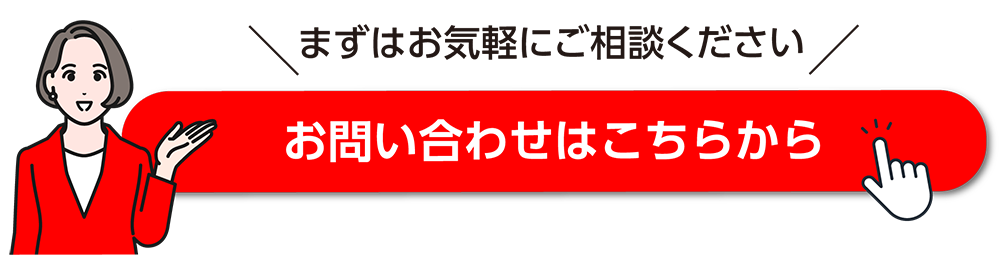
▼この記事を読んだ方はこちらの記事もおすすめ!